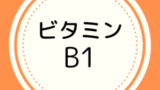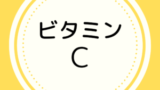ランキングの数値は可食部100g当たりの数値となっています。
ランキングの抽出方法
- 食品成分データベースの検索機能を参照
- 日本食品標準成分表2020年版(8訂)で最終確認
栄養ランキング ダウンロード資料(ダウンロードしたい方はこちら)
サムネイルのアイコンをクリックするとダウンロード画面に移行します。
ランキングの掲載条件
- 水分含有量30g以上
- 「生」「焼き」「ゆで」がある食品は「生」を採用とする
- 複数の品種がある場合は代表的なものを掲載
水分含有量30g以上
水分含有量を無視すると乾物がランキングの上位を占めてしまうため。
30gの理由は当サイトのさじ加減です。
下の表を見れば水分の少ない粉状や乾物が多くなります。
水分が少ないので使う場合は数値の1/100〜1/10になります。
| No. | 食品群 | 食品名 | 鉄分量 | 水分量 |
| 1 | 調味料及び香辛料類 | バジル 粉 | 120mg | 10.9g |
| 2 | 調味料及び香辛料類 | タイム 粉 | 110mg | 9.8g |
| 3 | いも類 | 赤こんにゃく | 78mg | 97.1g |
| 4 | 藻類 | あおのり 素干し | 77mg | 6.5g |
純粋に赤こんにゃくの鉄分が破格ですね。
「生」「焼き」「ゆで」がある食品は「生」を採用とする
食べる時は「焼き」や「ゆで」状態で食べるが、買い物する時は生の状態で買い物をするため。
「焼き」や「ゆで」は「生」よりも成分値は高くなるが「生」を採用。
※栄養士が集団給食で発注する場合は廃棄率、栄養損失率、茹でた時の縮小分も加味していますが、栄養士以外の人をターゲットとしているので、栄養士の方のご指摘はご容赦ください。
※通常生食しないものは例外としてその都度表記します。通常かどうかの判断は当サイトの裁量とさせていただきます。
| 1 | 鶏卵 | 卵黄 生 | 4.8mg |
| 2 | 鶏卵 | 卵黄 ゆで | 4.7mg |
| 3 | 鶏卵 | 卵黄 乾燥卵黄 | 4.4mg |
| 4 | うずら卵 | 全卵 | 3.1mg |
| 5 | あひる卵 | ピータン | 3.0mg |
この場合の適正ランキングはこうなります。
| 1 | 鶏卵 | 卵黄 生 | 4.8mg |
| 2 | うずら卵 | 全卵 | 3.1mg |
| 3 | あひる卵 | ピータン | 3.0mg |
複数の品種がある場合は代表的なものを掲載
牛肉のバラ肉を食品成分データベースで「うし ばら 生」と検索すると・・・

| 品種名 | 説明 |
| 和牛肉 | 黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4種類。 飼育されている和牛の90%は黒毛和種 |
| 乳用肥育牛肉 | ホルスタイン種の雄子牛を20か月程度まで肥育。 国産牛と表示して市販されている例が多い。 |
| 輸入牛肉 | オーストラリア、米国からのものが多い。 品種はアンガス種やヘレフォード種といった肉専用種が多いものの、 [輸入牛肉]の品種は特定されていない |
| 子牛肉 | ホワイトといわれる子牛の肉を試料とした。 |
| 交雑牛肉 | 雌の乳用牛に雄の和牛を交配して生産された牛 |
一般的に流通している肉は、「国産牛」が多いため乳用肥育牛肉を採用する
各食品群の決め事
極力食べられる形状でランキングをしております。
熱を入れることで栄養素が損失する場合(VB群、VCなど)は「生」よりも「ゆで」や「焼き」を優先とする
| 穀類 | [水稲めし]を採用 |
| いも類及びでん粉類 | 皮あり/皮なし 「蒸し」、「水煮」を採用 ※「生」を採用しない理由 →食用する場合は「蒸し」の方が多い →「生」と「蒸し・水煮」で水分量が大幅に変化しないため |
| 豆類 | 「ゆで」、調理されたものを採用 |
| 種実類 | 「ゆで」を優先して採用 |
| 野菜類 | 「生」を優先して採用 生食しないものは「ゆで」や「焼き」を採用 |
| 果実類 | 「生」を優先して採用 ジャムやジュースは基本的には不採用 |
| きのこ類 | 「ゆで」→「生」の順番で採用 |
| 藻類 | 水分30g以上のものを採用 ひじきはステンレスを採用 |
| 魚介類 | 「生」を採用→「ゆで、焼き」は基本採用しない 調理したものは独立して採用 |
| 肉類 | 「生」を採用 うし→乳用肥育牛 ぶた→大型種肉 にわとり→若どり ・調理したものは独立して採用 ・もも、ロース、ヒレ などはそれぞれ採用 |
| 卵類 | 「生」を採用 全卵、卵白、卵黄はそれぞれカウントする |
| 乳類 | 普通牛乳を採用 ナチュラルチーズはそれぞれカウントする |
| 採用しない食品群 | 油脂類 砂糖及び甘味類 し好飲料類 調味料及び香辛料類 調理加工食品類 理由は以下の通り ・1品で食べることがないため ・添加物の量によってランキングのバランスが悪くなるため |